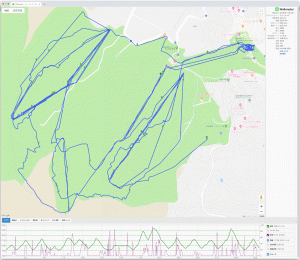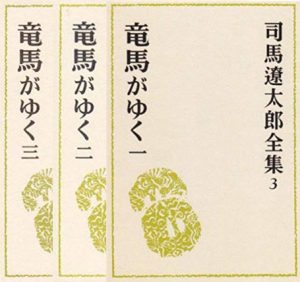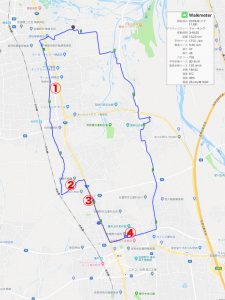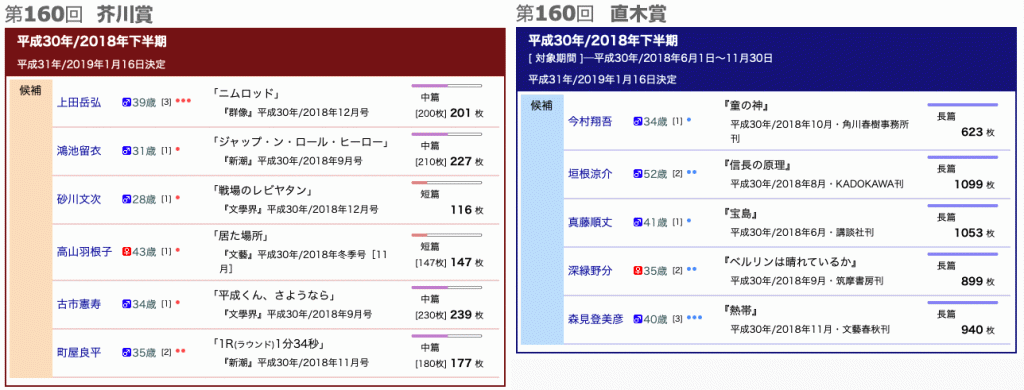昨日出かけた斑尾スキー場の帰りに近くの道の駅に寄ってみました。その名を「ふるさと豊田」と言うところで、毎年この時期に立ち寄る道の駅です。中の様子を撮ったのが、右の写真です。どうでしょう、両側にりんごが勢ぞろいした様は何とも立派です。年が明け、この時期になると県内の大方の売場ではりんごはメジャーではなくなって品も少なくなるのですが、ここでは堂々としています。それもそのはず、まだまだりんごが美味しいのです。早速、購入して家で割ってみると蜜がたっぷり、そしてシャキシャキ感もあってとても美味しくいただきました。収穫してからだいぶ日にちは経ったのでしょうが、どのように保管していたのか、どうして中野市のりんごは保存状態がいいのか、いつもながら感心しました。
昨日出かけた斑尾スキー場の帰りに近くの道の駅に寄ってみました。その名を「ふるさと豊田」と言うところで、毎年この時期に立ち寄る道の駅です。中の様子を撮ったのが、右の写真です。どうでしょう、両側にりんごが勢ぞろいした様は何とも立派です。年が明け、この時期になると県内の大方の売場ではりんごはメジャーではなくなって品も少なくなるのですが、ここでは堂々としています。それもそのはず、まだまだりんごが美味しいのです。早速、購入して家で割ってみると蜜がたっぷり、そしてシャキシャキ感もあってとても美味しくいただきました。収穫してからだいぶ日にちは経ったのでしょうが、どのように保管していたのか、どうして中野市のりんごは保存状態がいいのか、いつもながら感心しました。
2025年10月 日 月 火 水 木 金 土 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31