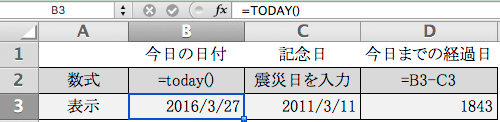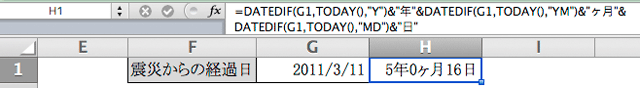今日のExcel シリーズは日付操作に関わる小技で、以下の課題を選びました。
① 現在日の表示ならびに記念日からの経過日を計算する
② 経過日を年月日で表示する
まずは①の例を以下に示します。
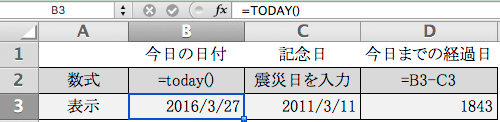
現在日の今日の日付とは、Excelでファイルを開いた日に合わせて、その日を表示するもので、上記の例ではB3のセルが本日投稿日の3月27日と表示されたものです。B3のセルには、その計算式を =TODAY() とすればOKです。次にある記念日から現在日までの経過日を計算するのは単純に引き算をすれば、ことが済みます。上記の例では、C3のセルに震災日を入力してD3のセルに、その計算式 =B3-C3 を入力すると、経過日は1843日となります。
②では、経過日を年月日で表示させる方法です。例として、①の経過日 1843日では味気ないので、以下に②の課題に沿った表示例を示します。
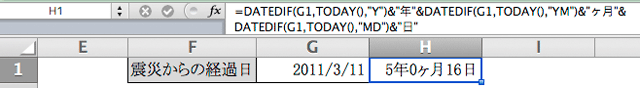
上記ではG1のセルに入力された日にちと現在日との相違を H1の計算式で求めたもので、結果は年月日で表示されます。ポイントは計算式に DATEDIF を使って、
=DATEDIF(G1,TODAY(),”Y”)&”年”&DATEDIF(G1,TODAY(),”YM”)&”ヶ月”&DATEDIF(G1,TODAY(),”MD”)&”日”
とするところです。ところで、数字に混ざって文字が表示されますが、前回に示した応用で、&”任意文字” の最後尾に & を加えると、計算結果の数値の間にも文字を挿入することができます。
本日のテーマはその活用範囲が限定されると思いますが、私は購入品リストなどの記録ファイルに経過日を求める欄を設けたりしています。
テレビや冷蔵庫の家電品、パソコン本体や周辺機器の経過日など、時おり眺めては「もうこんなに経ったのか」はまあいいとして、自分の結婚記念日などを入力すると、ハッとするどころでは済まなくなったり...
 すっかり春めいた安曇野です。写真は昨日、近くで撮ったものです。一昨日の雨で、常念岳もドサッと雪が落ちました。傍の桜も八部咲きから満開の勢いです。春ですねえ〜。例年の花見宴会も次週予定していますが、時期がづれて葉桜にならないか心配してます。今は午前8時前、これから週末は外出して当ブログもお休みします。では、行ってきま〜す。
すっかり春めいた安曇野です。写真は昨日、近くで撮ったものです。一昨日の雨で、常念岳もドサッと雪が落ちました。傍の桜も八部咲きから満開の勢いです。春ですねえ〜。例年の花見宴会も次週予定していますが、時期がづれて葉桜にならないか心配してます。今は午前8時前、これから週末は外出して当ブログもお休みします。では、行ってきま〜す。




 4月に入り、急に暖かくなってきました。芝メンテの業者さんからは芝生に水を撒くように言われ、ガーデニングの方も急に忙しくなってきました。今日は畑仕事です。土をおこし苦土石灰と堆肥を混ぜて整地しました。今日のところは、人参とごぼうの種を蒔き、レタスの苗を植えました。これからはご近所さんとも畑外交のスタートです。
4月に入り、急に暖かくなってきました。芝メンテの業者さんからは芝生に水を撒くように言われ、ガーデニングの方も急に忙しくなってきました。今日は畑仕事です。土をおこし苦土石灰と堆肥を混ぜて整地しました。今日のところは、人参とごぼうの種を蒔き、レタスの苗を植えました。これからはご近所さんとも畑外交のスタートです。 山梨県北杜市にある山高神代(ヤマタカジンダイ)桜が見頃になったと言うことで、本日、うちのオバはんと桜見物に出かけました。この桜は樹齢およそ2000年と言われるエドヒガンの古木で、古さは日本一のようです。まるで、イエス・キリストと同じ生まれではないですか。初めて見ましたが、写真よりもこじんまりとしていて如何にも古木でよくぞ咲いてくれたと言った感じです。それでも、咲いた桜の花自体には古さは微塵もなく、8分ほどに咲き誇っていました。立派です!お寺の境内は古木に混ざって、他の桜や花々が一斉に咲き、遠く甲斐駒ヶ岳も顔を出して、春爛漫この上なしです。お見事!今日はさほど混んでいませんでしたが、駐車場係は「明日は満開で、人出のピークは甲府まで連なる大渋滞だ」と言ってました。今日来て、よかった!
山梨県北杜市にある山高神代(ヤマタカジンダイ)桜が見頃になったと言うことで、本日、うちのオバはんと桜見物に出かけました。この桜は樹齢およそ2000年と言われるエドヒガンの古木で、古さは日本一のようです。まるで、イエス・キリストと同じ生まれではないですか。初めて見ましたが、写真よりもこじんまりとしていて如何にも古木でよくぞ咲いてくれたと言った感じです。それでも、咲いた桜の花自体には古さは微塵もなく、8分ほどに咲き誇っていました。立派です!お寺の境内は古木に混ざって、他の桜や花々が一斉に咲き、遠く甲斐駒ヶ岳も顔を出して、春爛漫この上なしです。お見事!今日はさほど混んでいませんでしたが、駐車場係は「明日は満開で、人出のピークは甲府まで連なる大渋滞だ」と言ってました。今日来て、よかった!
 今日は古式日本の年度末。自分にとっての年度末と言えば、例のピアノ課題曲、モーツァルト、ピアノソナタK545「第1楽章」の最終日です。本シリーズも前投稿から悠に2ヶ月が経過しましたが、練習もボチボチと続けてきて、今日でいよいよ最後です。結論からすると、目標未達でした。内田光子先生のCDソースを130%スピードダウンした位まではなんとか弾けるようになったのですが、目標の125%ではまだノーミスで弾けていません。余裕も何もなく、がむしゃらに鍵盤を叩きまくっても途中であえなく撃沈です。この5%の差は絶大で私にとっての限界を思い知らされました。思えば、期首の頃は全くのノー天気で、時間はたっぷりあるし、ゆでガエルだって知らず知らずに湯が沸騰するまで泳げるのだから、曲のテンポなんて徐々に上げていけばどうにでもなるさ、と楽観視していました。でも、違っていました。限界は必ずあって、そしてそれは予想外に近くにありました。それでも、目標の125%に近づけたので、まあよしとしましょう。原曲指定のアレグロではなく、限りなくアレグレットに近いモーツァルトは華麗さを失って堅実な手堅さが前面に出てしまいますが、その分、疾走する暴れ馬ではなく、のんびりと景色を楽しむ観光馬車のように弾く方が、自分に合っているように、今では思っています。そうです、速さのトゲトゲしさよりもゆっくりとした流麗さを磨くことにしました。明日から新年度で新たな挑戦をしようと思っていますが、このK545はこれからもずっと弾いていくつもりです。そうしないと、すぐに弾けなくなってしまう由...
今日は古式日本の年度末。自分にとっての年度末と言えば、例のピアノ課題曲、モーツァルト、ピアノソナタK545「第1楽章」の最終日です。本シリーズも前投稿から悠に2ヶ月が経過しましたが、練習もボチボチと続けてきて、今日でいよいよ最後です。結論からすると、目標未達でした。内田光子先生のCDソースを130%スピードダウンした位まではなんとか弾けるようになったのですが、目標の125%ではまだノーミスで弾けていません。余裕も何もなく、がむしゃらに鍵盤を叩きまくっても途中であえなく撃沈です。この5%の差は絶大で私にとっての限界を思い知らされました。思えば、期首の頃は全くのノー天気で、時間はたっぷりあるし、ゆでガエルだって知らず知らずに湯が沸騰するまで泳げるのだから、曲のテンポなんて徐々に上げていけばどうにでもなるさ、と楽観視していました。でも、違っていました。限界は必ずあって、そしてそれは予想外に近くにありました。それでも、目標の125%に近づけたので、まあよしとしましょう。原曲指定のアレグロではなく、限りなくアレグレットに近いモーツァルトは華麗さを失って堅実な手堅さが前面に出てしまいますが、その分、疾走する暴れ馬ではなく、のんびりと景色を楽しむ観光馬車のように弾く方が、自分に合っているように、今では思っています。そうです、速さのトゲトゲしさよりもゆっくりとした流麗さを磨くことにしました。明日から新年度で新たな挑戦をしようと思っていますが、このK545はこれからもずっと弾いていくつもりです。そうしないと、すぐに弾けなくなってしまう由...
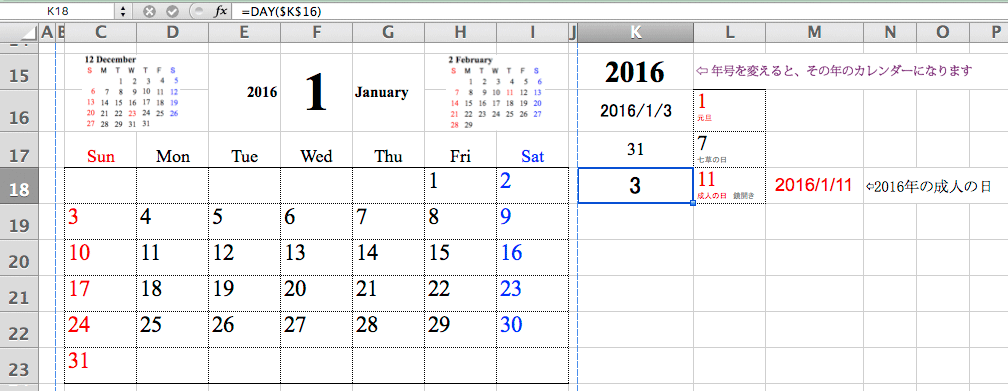
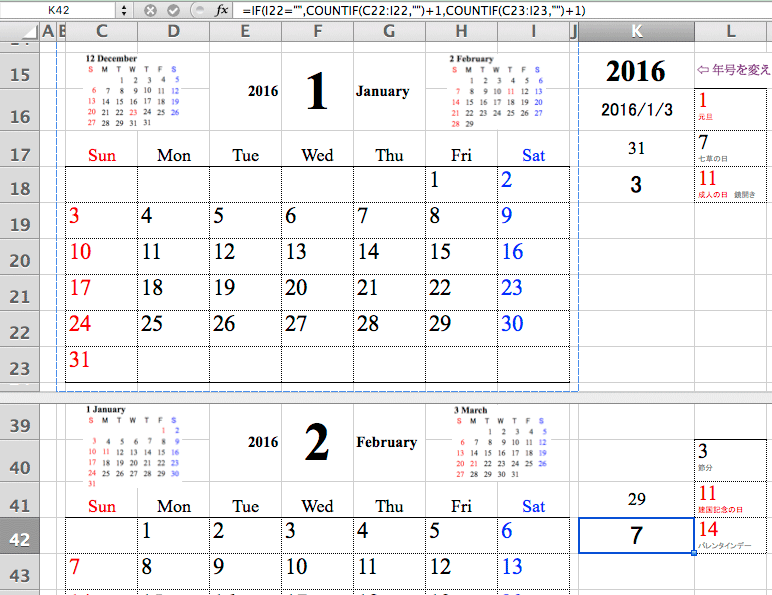
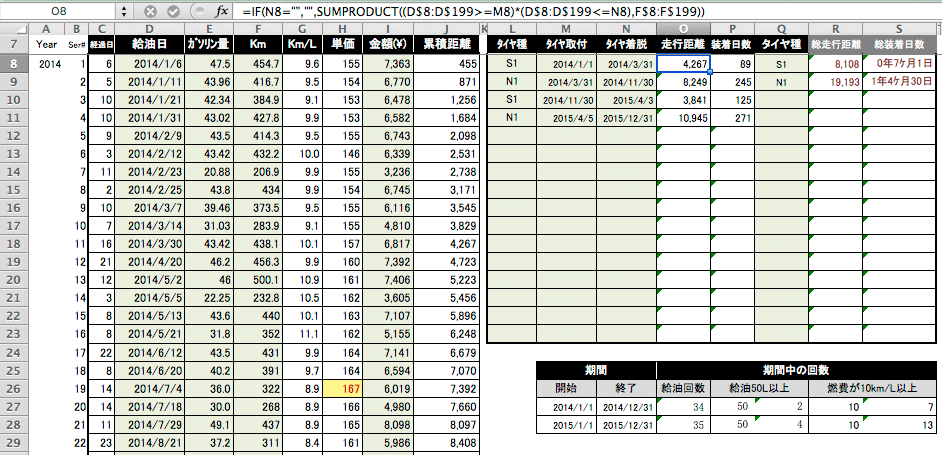 ②の課題では、複数の検索条件に一致するすべてのセルの個数を求める COUNTIFS 関数を使っています。上記の右下の表で、2014/1/1〜2014/12/31の1年間で給油時に記録した燃費が10Km/L以上が何回あったかの回数を求める計算式は、
②の課題では、複数の検索条件に一致するすべてのセルの個数を求める COUNTIFS 関数を使っています。上記の右下の表で、2014/1/1〜2014/12/31の1年間で給油時に記録した燃費が10Km/L以上が何回あったかの回数を求める計算式は、